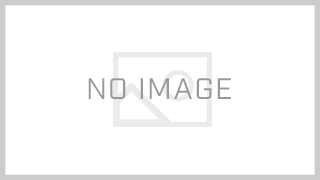ダダイズムの詩

吉増剛造の初期の詩がダダイズムの影響を受けていると知ってから、ダダイズムに興味を持つことになった。
高校の頃便覧で勉強した知識で、高橋新吉の『ダダイスト新吉の詩』と萩原恭次郎の『死刑宣告』という詩集が存在することを知っていたので探してみることにした。
大学生の頃の話だ。
大学の図書館の詩の棚にはなく、書庫から引っ張り出してきた気がする。
書庫の本は頼んで持ってきてもらうのだったか、自分でとりにいくのだったか。
おぼろげに地下の書庫の薄暗い感じと、非常口の緑のランプの光景を覚えているので、普通の学生でも出入りできたと思う。
ところで、早稲田大学の図書館は卒業生であれば利用出来るのだったと思う。
老後、早稲田周辺に住めば図書館で読書三昧の日々が送れると考えたが、それは結局近所の図書館でも同じか。
取り寄せに時間がかかっても構いやしないので。
大学の図書館と言えば、中央図書館と学部の図書室があった気がする。
政治経済学部の図書室には江戸川乱歩がメモ書きした本が残っている、と高橋世織教授が言っていた気がするが、結局どこにあるのか分からず見ずに終わった。
話をダダイズムに戻すと、『ダダイスト新吉の詩』は当時それほど印象に残らなかった。
一方『死刑宣告』は強烈だったのでよく覚えている。
強烈なのは内容というよりは見た目だ。
文字を絵として見せてやろう、という感じのもの。
詩人を極めたらこういう方向に行くのかと思った。
吉増剛造もだんだんこのような感じになっている。
衝撃は受けたのだが、文字を絵のように見せる方向へ行くのはなんとなく理解ができてしまう。
言葉を極めた人々なのだから、そんな単純なものではなく、複雑な理由により絵画化して行ったのだろうが、素人である私から見るとただの活字の絵画化に見えてしまう。
そのような冷めた思いから、やはりある程度の縛り、拘束があった方が詩としての凄みが出て来るのではないかと考えるようになった。
なので初期ビートルズを良いなあ、と思うのと同じ感覚で、初期吉増剛造が良いなあ、と思うのだ。
この観点を掘り下げると面白い発見があるかもしれない。
極端な話、初期ピカソとか。
行くところまで行った人の初期の作品。
キューブリックやタルコフスキーの初期の作品とか。
文字の絵画化の逆を突き詰めたもの、縛り拘束がきついもの、俳句の世界はこれに近いと思う。
五七五の制限の中で、季語というものが発明され、いろいろなイメージを詰め込んだのだ。
俳句の世界は俳句の世界で、自由律のものを是とするか、という論争もある。
自由律の俳句とは不思議なもので、ちゃんと俳句らしさが感じられる。
ただ、縛りの中での無理やり組み合わせや言葉遣いが産み出す反応のようなものは薄れる。