構造主義は学問としてドラマティック
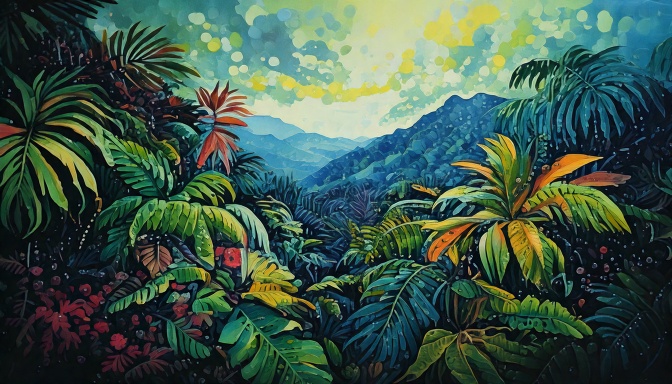
構造主義を知ったのは、早稲田大学で現代思想の講義を受講してからだ。
その講義はポストモダンが中心で、フーコー、ドゥルーズなどを扱った。
ドゥルーズの『マゾッホとサド』から、サドの『閨房哲学』からマゾッホの『毛皮を着たヴィーナス』などを扱った。
バタイユの『眼球譚』なども。
フーコーのパノプティコンもそれで知ったし、そういえば科学哲学も扱った。
ポパーの疑似科学の見分け方やファイヤアーベントのAnything goes。
Anything goesからは自由を感じたものだ。
そう言えばウィトゲンシュタインも扱った。
そこから思想に興味を持ち、ポストモダンがポスト構造主義とも言われていたことから、構造主義に興味を持った。
社会には関数のような構造が潜んでいる、という考えと理解した。
これはそれほどピンと来なかった。
ピンと来なかったというよりかは、当然のことのように思った。
そもそも経済学を筆頭に社会科学とはそういう考えではないのか。
構造主義以前はそうではなかったのだろうか。
そんなはずはない。
マルクスやケインズは構造主義以前だろう。
などと考えつつも、構造主義の良さというものが最近わかるようになった。
学問としてドラマティックということだ。
言語学のソシュールに社会人類学のレヴィ=ストロースがなぜ影響を受けたのかということだが、アメリカで言語学のヤコブソンと出会うのだ。
お互いがそれぞれの学問に興味を持ちながら、知的に影響し合って言語学の手法が人間社会にも応用できるということに気づいた。
この応用の成果によって、西洋中心主義のサルトルを黙らせた。
この点が知としてダイナミックでドラマティックだ。
しかし、私は構造主義に共感を得ながら、生き方の考え方としてはサルトルが好きだ。
実存主義。
死んだら終わり主義。
科学としてではなく、文学的芸術的に心に響く。
だが、サルトルに傾倒してしまうのは苦しい。
自由の刑に処せられているなんて。
自由は明るく楽しいものであってほしい。







