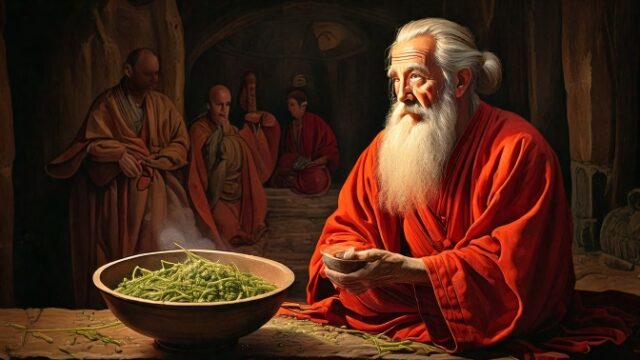アイコンとしての十字架

宗教のことを語る時は慎重にならねばならない。
特に他意なしということで以下の文章を書いていく。
リトアニアいつか行ってみたいということがあるので、ネットで色々調べたところ「十字架の丘」という場所が出てくる。
十字架がたくさん立てられている丘なのだが、こういう宗教的なものが連続すると、なんというか、物々しいというか、凄みというか、そういうものを感じる。
日本で言えば、伏見稲荷大社の鳥居の連続とか、三十三間堂の1001体の観音様とか、そういうものも同じ感覚になる。
極めて客観的になると、言い換えると、自分に無知のヴェールを着せて考えると、十字架は格好良いと思う。
十字架が格好良いというのは、十字架のネックレスなど存在することが示している。
あれはキリスト教圏ではどのような扱いなのだろう。
お守りのような意味合いになるのだろうか。
元々は磔刑に使われたものから来ていると思うのだが。
日本では、漫画のイメージだが「悪霊退散」と言いながら神父さんが十字架をかざす場面が浮かぶ。
よくよく考えたら、十字のデザインである国旗が多いが、これらはキリスト教から来ているとみて良いのだろうか。
十字架をシンボルとして団結していると考えられるので、アイコンとしての十字架は強力だ。
冒頭に戻ると、リトアニアの「十字架の丘」の多数の十字架は、背後に団結を感じて捉えると猛烈なエネルギーを感じ取ることができる。
団結とアイコンということを考えると、鉤十字というものがある。
これはナチスに利用され、ずっと前らから存在している鉤十字からしてみれば気の毒なことになった。
ナチス登場前の鉤十字のイメージ、ナチスがシンボルとして採用した時のイメージはどのようなものだったのかが気になる。
ヒンドゥー教や仏教から来ているという話があるが、いかに。