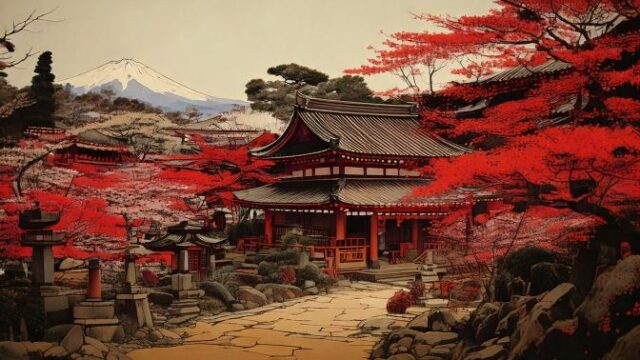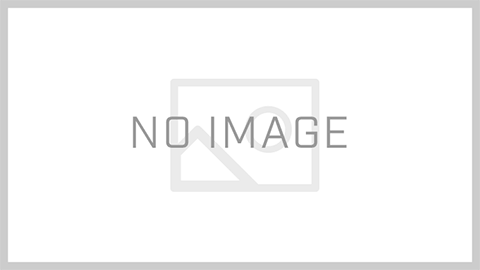会津八一と釈迢空は似たようなイメージで取っ付きにくい

スポンサーリンク
定期的にブックオフの110円コーナを物色する。
自炊で本をスキャナーで取り込んで、NASに保存するようになってからこの習慣が出来た。
文庫や新書は裁断しやすいし、スキャンしやすい。
110円でデータとして本が保有できるなんてなんともお得だ。
偏見も入っているが、特に岩波新書と講談社現代新書は保有している嬉しさのようなものがある。
最近岩波新書で永田和宏の『近代秀歌』を手に入れた。
細胞生物学者でもあるということを知った。
こういう、科学としての研究も創造としての短歌もできるなど嫉妬を感じざるを得ない。
俳句でも有馬朗人など、なんでもできる人はいる。
短歌にしろ俳句にしろ、何か美とされるものの裏側には論理や理屈があるということか。
泥酔した詩人がインスピレーションで発した言葉は偶然美しいだけということなのだろうか。
それはさておき、なんでもできる人にはジェラシーが邪魔をして、それほど興味や共感が持てないのだが、パラパラと『近代秀歌』を読んでいたところ、会津八一と釈迢空は苦手だと書かれていた。
これには非常に共感した。
特に会津八一は短歌はもちろん、美学と書と仏教など、私が興味あるもの全てできる達人なのでなんとか理解したいのだが、それほど心にグッとこない。
釈迢空も民俗学者で理解したいと思うのだが強烈にこころに響くものがない。
「人も 馬も 道ゆきつかれ死にゝけり。旅寢かさなるほどの かそけさ」
強烈に心にはこないが、なんとなく良い。
ふんわりと心にくる。
会津八一も同様。
会津八一や釈迢空の文章をすらすらと読めるようになりたいものだ。